データでまちづくり?EBPM(エビデンスに基づく政策立案)ってなんだろう
最近よく耳にする「EBPM」。Evidence-Based Policy Making の略で、「エビデンスに基づく政策立案」と訳されますが、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。 でも実は、都市政策やまちづくりの現場でじわじわ広がっている考え方です。
元々は医療の現場でEBM(エビデンスに基づく医療)が重要視されるようになり、それが政策分野に波及したのがEBPMです。データや調査を根拠に、よりよい判断をしていこうというこの動き。 今回はその概要と実際の使われ方をざっくりまとめてみました。
感覚や声の大きさで決まる意思決定から「根拠ある意思決定」へ
これまでの政策は「前例があるから」「みんなそうしてるから」「地元の有力者が言ったから」で決まっているものも少なくありませんでした。一方でEBPMでは、ちゃんとした根拠=エビデンスをもとに考えることが大事にされています。たとえば…
- どこに図書館を新しくつくれば、多くの市民が利用しやすい?
- 子どもの遊び場、どんな場所につくれば人が集まりやすい?
- 高齢者の買い物や通院、バス路線をどうすれば便利になる?
こういう問いに対して、感覚や印象だけでなく、データや過去の実績から考えていこうという考え方です。
どうやって実践されてる?
国は内閣府や内閣官房を筆頭にEBPMの推進体制を整え、各省庁や自治体等のEBPMの推進・旗振りを行っています。
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html
例えば、内閣官房行政改革推進本部事務局は「EBPMガイドブック」を公開し、行政内の政策担当者に向けたEBPMの進め方についての助言を行っています。
https://www.gyoukaku.go.jp/ebpm/shien/index.html
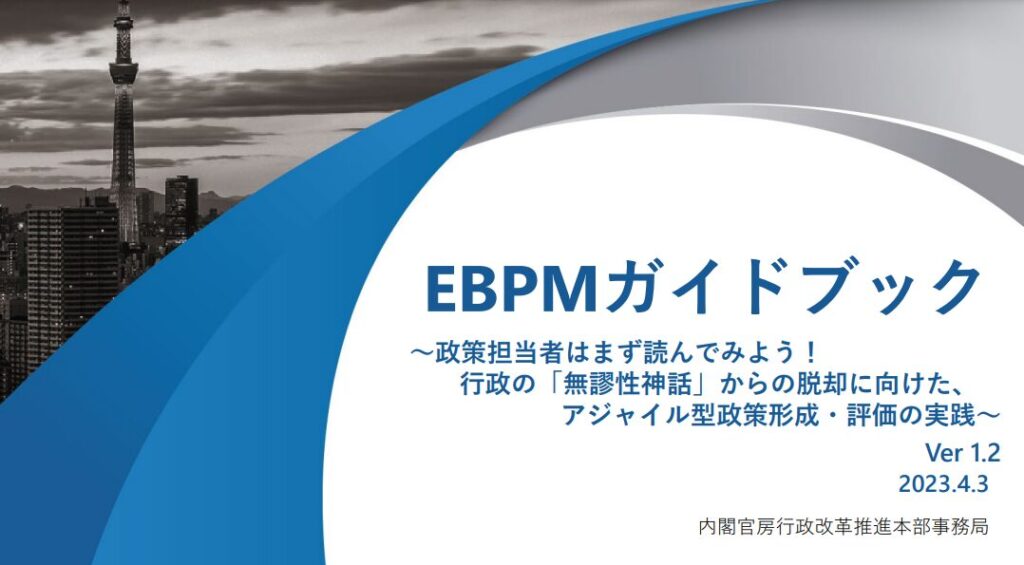
ガイドブックは実に120ページ!単に「エビデンスを意識しましょう」と啓発している訳でなく、政策形成~評価までの一連のプロセスについて、各プロセスごとの実践的なEBPMの導入方法が記載されています。行政内での政策遂行の過程が見て取れるようで、行政担当者はおろか、一市民として一度は目を通しておきたい内容ともいえます。
機動的で柔軟なアジャイル型政策形成・評価/ダイナミック(動的)なEBPM
EBPMガイドブックでは従来の政策形成・評価に対して「機動的で柔軟なアジャイル型政策形成・評価」が提唱されています。
従来型とは…
・現状維持を前提にPDCAが回る
・政策評価を一時点でのみ行う(静的なEBPM)
・課題があってもエビデンスが無ければ取り組まない
対するアジャイル型とは…
・PDCAを回し、かつ環境変化に対応しながら政策効果を上げることを追求(動的なEBPM)
・経験のない課題についても、考えうる最善の政策をもってトライ&エラー。常に臨機応変に。政策効果(インパクト、アウトカム)の追求を行う。
また、動的なEBPMとは
・評価・分析や見直し自体が目的化しないよう留意しつつ
・政策効果を上げることを追求して、政策を機動的で柔軟に立案・修正できる政策サイクル(PDCA)を回すこと
との言及があります。
動的なEBPMの政策サイクル
- ファクト発見(課題の発見と政策目標の設定)
現場の課題をコミュニケーションやデータ分析を通じて発見する。 - 政策分析(政策手段の検討)
ロジックを明確化し、既存の知見(文献・事例)や統計データ、定性情報などから複数の政策手段を洗い出し、それぞれの効果や実現可能性を比較検討する。 - モニタリングや評価の事前設計
モニタリング指標を設定します。特に目標と進捗にはズレが生じる前提での設計が必要です。また、状況によって別の政策手段に切り替えるための切り替え条件の設定も重要です。 - モニタリング
施策を実行した後は、モニタリングや現場とのコミュニケーションをもとに実態把握に努めます。また当初想定から乖離が生じた場合は次の「業績マネジメント」に移行します。 - 業績マネジメント(評価・分析)
中間や事後の効果検証を行い、政策の停止や別手段への転換の必要性を判断します。 - 運用改善、政策の入れ替え、次の政策立案(政策転換)
政策が思い通りに進まない場合、政策運用や政策手段を見直します。
このように、EBPMとは単に「データを見て政策を立てる」だけでなく、課題設定~政策立案~状況確認の、各工程にわたってデータを横に置きながら臨機応変な意思決定を行うことを指し、そのような政策遂行がこれからの時代においては重要視されているとも言えます。
ロジックモデルで全体像を整理する
EBPMの実践にあたっては、因果関係の解明やエビデンスの収集方法、効果測定の設計方法など、いくつかの概念の整理が必要となります。これらのうち今回は、ロジックモデル(政策目的とロジックを明確化する過程のフレーム)についてご紹介します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 現状把握 | 社会加地への着眼 |
| インパクト設定 | 国民・社会のあるべき姿・ありたい姿の定義 |
| 課題設定 | 社会課題の根本原因を特定 |
| アウトカム設定 | 政策により生み出した意識や行動の変化(行政側でコントロールできない受益者視点での変化) ※SMART(明確、測定可能、達成可能、現実的、期間限定の政策目標の設定にあたり重要な5要素の総称)な政策目標を設定する必要がある。 |
| アウトプット設定 | 活動に投入する資源(人、予算など)など、行政側でコントロール可能な指標。 |
| アクティビティ | 実際に行う施策・サービス |
| インプット | 予算、税、規制、計画などの、政策手段。 |
| 測定指標の設定 | 上記の各項目について、達成度が客観的・多段的・短期間に測定・把握できるよう、測定指標を整理。 |
この構造を整理することで、エビデンスに基づいた仮設立案や政策の検討が進み、また「本当に目的に近づいているか?」を確認しながら政策遂行ができるようになるため、臨機応変な意思決定や計画変更が進むようになります。
使えるデータってどこにあるの?
意外と身近なところにあります。
- e-Stat(政府統計)
- 自治体のオープンデータ
- GIS(地図に情報を重ねる)
- 住民アンケートやSNSの声
- 他の自治体の事例
グラフにしたり、地図で見せたり、ストーリーで伝えたり。 難しそうなデータも少し見せ方を工夫すれば伝わりやすくなります。本サイトでも今後、EBPM視点で日本国内にどのようなデータがあり、使えるかを整理していきたいと思います。
まとめ
EBPMは「政策の決め方・経過をを見える化」するための考え方といえます。今回は、最近まちづくりの現場でも注目されている「EBPM(エビデンスに基づく政策立案)」について見てきましたが、次回の記事では、実際にどんな地域でどんなふうに使われているのかリアルな事例をもう少し深掘りしてみたいと思います。
なお、もちろん、すべての政策がロジックやデータだけで決まるわけではありません。社会には、信念や文化、過去の積み重ね、個人の想いといった、数字では測れない大事な要素もあります。それでも「なんでこの政策なの?」という問いに、きちんと答えられるようにすることは重要なことです。納得や信頼を得ながら進めていくために、EBPMは確かな後押しになります。
まちづくりに関わる人はもちろん、「データってどう使えばいいんだろう」と思っている人にとっても、EBPMのフレームワークは活用・転用予知のある使える考え方かもしれません。まずは身の回りの「なぜ?」を、データと一緒に見つめてみることを意識し、このサイトでも引き続き取り扱っていきたいと思います。

